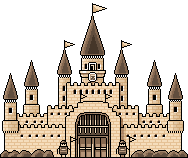�������̎Ў���
1999�N�i����11�N�j��12��2���A�����b�R�̃}���P�b�V���ŊJ�Â��ꂽ
��23�E��Y�ψ���ɂ����āA
�u�����̎Ў��v�����E������Y�ɓo�^����܂����B
���E��Y�ɓo�^���ꂽ�u�����̎Ў��v�̓��e�́A
�����R���ɂ����r�R�_�ЁA���Ƌ{�A�։�����103���i����9���A�d�v������94���j
�́u�������Q�v�ƁA�����̌������Q����芪���u��Ձi�����I�i�ρj�v�ł��B
�����Ɛ_�����Z�������Ǝ��̐M���炭��ł�������
��r�R�i�j�̎R�j���͂��ߏ��R�̐_����J���Ă�����r�R�_�ЁA
1200�N�ȏ�̗��j��L��������R�։����ɑ�\���������̎Ў��́A
�_�Ƃ��Đ��߂镧���Ɛ_�����Z�������Ǝ��̐M���炭��ł��܂����B
����4�N�i1868�N�j�̐_�������߈ȍ~�A�����R���̕������z���̂��ė։����ƌĂсA
���Ƌ{�ȊO�̓����R���ɓ_�݂���_�������̂��ē�r�R�_�ЂƌĂ�ł��܂��B
   
���v���Ԃ�Ƀ��t���b�V���ł��܂����I
|

�������Ƌ{�i�Β����j |
���ߖ@�Œ���������������悤�A
�Βi�͏�ɍs���قǕ��������A
��i�̍������Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B
 |

�������Ƌ{�i�O�_�ɁF��_�Ɂj |
�Z�q����̌����ɂ́A
�t�H�̍Վ��Ŏg����
�n�����ނ������߂��Ă���
������m��Ȃ��]�ˎ��㏉���̊G�t�E
���T�H�����G��`�������߁A
�u�z���̏ہv�Ƃ����Ă��܂��B
 |

�������Ƌ{�i�_�X�Ɂj |
�����n�̕a�C���������Ƃ���
�C���h�̌̎��ɂȂ����
�����`����Ă��܂��B
�u������E���킴��E��������v
�L���ȎO���̒���
 |

�������Ƌ{�i�������F�p���[�|�C���g�@�j |
���ʂɓ������A���ɗz����A
���̉��ɔq�a�E�{�a�B
����炪�d�Ȃ炸�Ɉ꒼���Ɍ�����ʒu���A
�k�C�̓��̋N�_�ƌ����A
�ł����͂ȃp���[�X�|�b�g�̈�B
�u�k�C�̓��v�Ƃ́A�k�ɐ����������Ƃ����Ӗ��B
�z����Ǝ�O�̒����� ���S�Ɍ����
�k�ɐ�������悤�Ɍ��Ă��Ă��܂��B
|

�������Ƌ{�i�z����j |
2017�N3���A44�N�Ԃ�A4�N�Ԃ�������
��C�����I���A�F�N�₩�ɂ�݂�����܂����B
������Ă��Ă��O���Ȃ����Ƃ���
�ʖ��u����̖�v�ƌĂ�Ă��܂��B
  |

�������Ƌ{�i����j |
���ɂ���{�Ђ����d�v�Ȗ�
��̗����̒��ɂ́A
�����E�~���������Ă��܂��B
 |

�������Ƌ{�i���{�F�p���[�X�|�b�g�A�j |
�u���{�v�͐��C�̔������I
�ƍN���̖���揊�u���{�v
�ɒʂ���u����L����v�̏㕔��
���܂�Ă���u����L�v
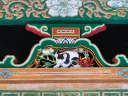 |

�������Ƌ{�i��_���i�p���[�X�|�b�g�B�j |
�u�Q���p���[�X�g���[�g�v
�������Ƌ{�����r�R�_�Ђ֑����Q����
�����p���[�̂���ʂ�
 |

������r�R�_�� |
�j�̎R�̎R���̓�r�R�_�Љ��{�ƁA
�����s���̓�r�R�{�Ђ̒��Ԃɂ���̂�
���{�K�ƌĂ�Ă��܂��B
 |

������r�R�_�Ёi�q�a�j |
���݂̖{�a�́A�]�˖��{�Q�㏫�R
����G���̔���ɂ��1619�N�ɑ��c
�i���݁A�C�����j
 |

������r�R�_�Ёi�_���j |
�����R���̓����A
��J��ɉ˂���ؑ���̐Ԃ���
���̐́A�[����������2�C�̃w�r������A
�����ė��ݍ������ɂȂ����Ɖ]���`��
 |

�����R�։����i�{���F�O�����j |
766�N������l�������������ƂɎn�܂�
810�N���삩�疞�莛�̏̍�����
�V��@�̎��ƂȂ�������
 |
 �����R�։�����Q�@�i�m����j �����R�։�����Q�@�i�m����j |
�����R�։����ɂ���R�㏫�R�ƌ��̗�_
�c���ł���u�ƍN���v�𗽂��ł͂Ȃ�Ȃ�
�Ƃ����⌾�ɂ��A
���ƍ����g�p���d���ŗ�������������
 |

�����R�։�����Q�@�i��V��j |
��V��͐Βi��ɂ��锪�r�O����ꉮ����̖�
���ʂ̍����i���j����삷��̂��u�����V�v�A
�E���i���j����삷��̂��u�L�ړV�v
  |

�����R�։�����Q�@�i�鍳��j |
����2�N(1653�N)��Q�@�ɑ��c���ꂽ��B
���������ׂă{�^���̉Ԃœ���
����Ă��邱�Ƃ���ʖ��u���O��v
 |

�����R�։�����Q�@�i����j |
������ŁA�����̑O��̌��𓂔j���`�B
��r��`���ŋ��n�ւ̕����ⓧ�����
�C�i���ӂ�鑕���ƂȂ��Ă��܂��B
 |

�����R�։����_��Q�@�i�c��Ö�j |
���̉@�̓�����ɓ������́A
�����l���̗��{����ŁA
�ʖ��y���{��z�ƌĂ�Ă��܂�
��̒ʍs������������̑�`�ɋ߂�
�A�[�`�^�ő����Ă���
���{����̍c�Ö�
|